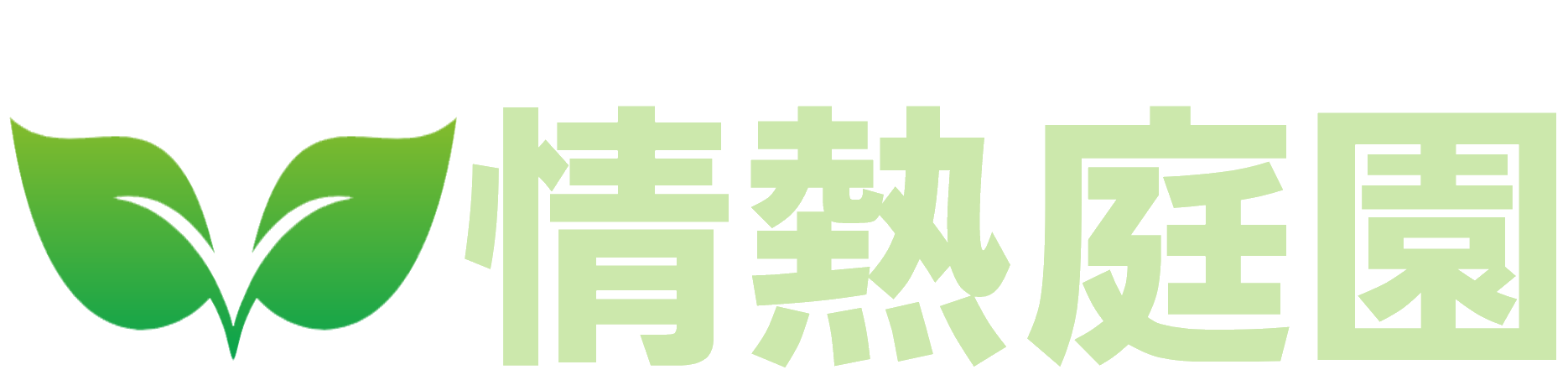Last Updated on 2024年5月21日 by Taichi
《そうだ、今週も京都に行こう》
9月下旬から11月上旬にかけての私(Taichi)の合言葉は
《そうだ、今週も京都に行こう》
私は、大阪北部の在住です。
同じ近畿地方とはいえ、京都に出向いて名勝・庭園を拝観するのは意外と時間がかかります。
気持ち的に億劫になることも度々。
マイクロツーリズムならではの悩みってやつです。
でもそんな時は、これまでの京都体験…
《少しの時間でも京都に行って良かった》
そんな体験を思い出しては京都に向かうのです。
さて今回の初秋の京都のターゲットは
京都市の北部、鷹ヶ峰にある【光悦寺】です。

光悦寺から鷹ヶ峯を。
徳川家康が本阿弥光悦に与えた地…鷹峰
江戸時代の芸術家である本阿弥光悦は、慶長年間(1596年 – 1615年)の初年にはこの地に別宅を構えていたが、元和元年(1615年)に徳川家康により付近一帯の土地を与えられた。Wikipedia
この土地を与えられた光悦さんは、様々な工芸を推進する場所としてこの地を発展させました。そして光悦さんが亡くなった後の1656年、この光悦さんの屋敷が【光悦寺】となったのです。
正直、このお寺【光悦寺】には、それほど期待してませんでした。
すぐ近くのお寺【源光庵】の、《悟りの窓》と《血天井》を見に行く流れで時間的にも丁度いいな~、と思った程度だったので。
これが大きく裏切られたのです。
江戸時代初期のスーパーアーティスト・本阿弥光悦の
不屈の精神と芸術的センスが生み出した《茶室ワンダーランド》
…そんなお寺です、【光悦寺】って。
めっちゃ入口がわかりにくい
源光庵から、バス停と反対向きに進んだ所に光悦寺の入口はあります。
入口が分かりにくいのですが、構えが偉そうでないのがナイス。

【光悦寺】の入り口 住宅と並んで何気なくある…
モミジと苔の参道を通っていきます。

【光悦寺】参道 狭いので参道内は撮影禁止
※紅葉の時期は参道からすでに、めっっちゃいい雰囲気だと思います。
※参道の中は撮影禁止なので気をつけて。
拝観料金400円(紅葉時:500円)を払ってさらに進みます。
本堂。光悦さんの御屋敷だったところですね。

【光悦寺】本堂
茅葺き屋根の鐘楼(しょうろう)茅葺の屋根の鐘楼を見たのは初めてです。
独得の雰囲気を持ってますね。

【光悦寺】茅葺屋根の鐘楼

【光悦寺】回遊式の庭園
境内全体が回遊式の庭園のような造りになっています。路地の一部などは七代目小川治兵衛が作庭したものなんだそう。
クネクネとした小道を歩きますと、境内には7つの茶室が点在しています。
こちらは茶室「三巴亭(さんばてい)」

【光悦寺】茶室のひとつ 三巴亭
茶室に入れるわけではありませんが、その隠されたような茶室の佇まいが素晴らしい。

大虚庵を囲む【光悦垣】
光悦寺の茶室を取り囲んである竹垣は”光悦垣”と呼ばれています。

【光悦垣】
日本の伝統的な竹垣の一つ。割り竹を粗い目の菱形(ひしがた)に組み
、割り竹の束をのせたもので、頂部がゆるい曲線を描く。◇近世初期
の芸術家、本阿弥(ほんあみ)光悦が好んだことに由来。コトバンク
大虚庵前の竹の垣根は光悦垣またはその姿から臥牛(ねうし)垣と呼ばれ徐々に高さの変る独特のものである。
庭園のそこかしこに、秋の気配が。
これはドウダンツツジかな…

秋の気配が…
鷹峰三山を眺める~京都絶景を拝むワンダーガーデン
光悦寺の庭園拝観のクライマックスは、茶室「徳友庵」。
光悦の号である「徳友斎」から名づけられたこの庵の縁側から眺める、素晴らしい鷹峰三山の景色。

徳友庵からの景色が素晴らしい
そして茶室「本阿弥庵」の手前からは鷹峰三山が全て見渡せます。
(鷹ヶ峯、鷲ヶ峯、天ヶ峯)

本阿弥庵から鷹峯を。
遠くに見えるのは、東山三十六峰。

本阿弥庵から。左側の遠くには東山三十六峰
境内の奥には本阿弥光悦の墓所がありました。合掌。

本阿弥光悦の墓所
徳友庵の隣には本阿弥家一族の墓所があります。

本阿弥一族の墓所
【光悦寺】とは
名 称:光悦寺(こうえつじ)
所在地:京都市北区鷹峯光悦町29
山 号:大虚山
創建年:明暦2年(1656年)
本 尊:十界大曼荼羅
開 山:日慈
茶 室:「妙秀庵」「本阿弥庵」「徳友庵」「大虚庵」「了寂軒」「騎牛庵」「自得庵」
指 定:京都市により歴史的風土特別保存地区に選ばれている
アクセス:市バス「源光庵前」下車、徒歩約3分
営業時間:8:00~17:00(紅葉時8:30~17:00)
拝観料 :通常400円(紅葉時500円)
定休日 :11/10~11/13
植物Fan.TaiChi
関連記事:京都・祇王寺の苔が最高!