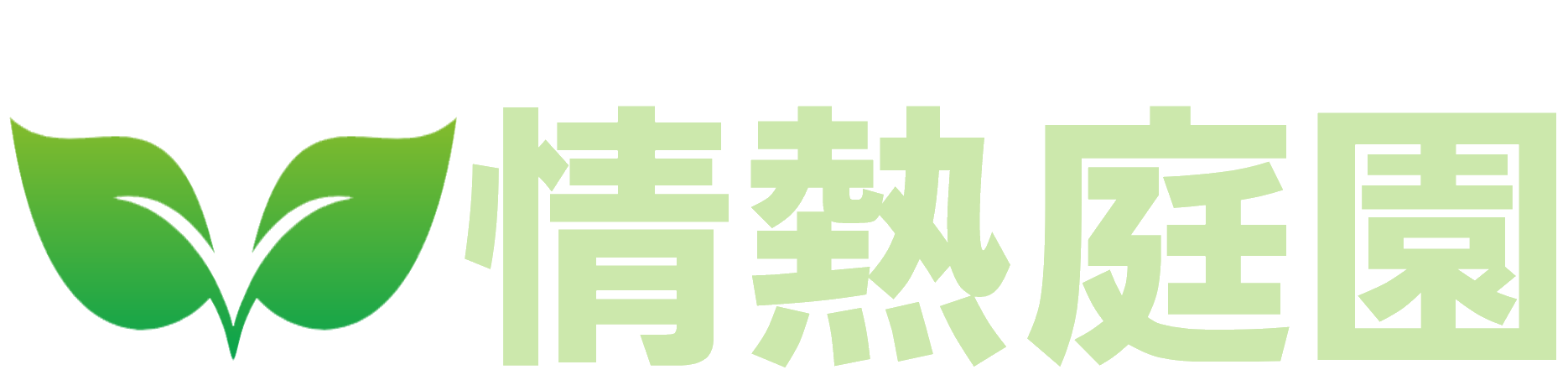Last Updated on 2021年6月12日 by Taichi
強靭な野草、カタバミ
黄色い花のカタバミは、我が家では「見かけたら即、抜く」という超・雑草扱い。

恐ろしい繫殖力で庭の厄介者【カタバミ】特に黄色い花の方が…
地下に球根を持ち、さらにその下に大根のような根を下ろす。匍匐茎をよく伸ばし、地表に広がる。このため、繁殖が早く、しかも根が深いので駆除に困る雑草の1種である。Wikipedia
カタバミって、世界に何種類もあるんだそうだが、ウチでよく生えてくる黄色い花のカタバミは、
・カタバミ
・アカカタバミ
・オッタチカタバミ
の3種。
葉っぱが赤い(銅葉)アカカタバミなんて、お気に入りの鉢植えの隙間に発見したら
それこそ絶望的な気分に襲われてしまう。

コイツが一番厄介者【アカカタバミ】
即、抜き取って壊滅させておかないと、放っておくと直根性で地中深く根が入り込み、なかなか抜けなくなる。匍匐茎が鉢土を這いまわると、とっても取りにくい。葉っぱだけがモゲてしまうこともしょっちゅう。
花がちょっと可愛いからと、うっかり残してしまうと種が跳ねて飛び散って、どんどん生え広がる。
ロクなことにならないが…
赤い花のカタバミは【イモカタバミ】

イモカタバミ
一方、赤い花のイモカタバミはイモ=塊茎で、根っこは直根ではなく、さほど強靭でない。
案外抜きやすいし黄色いカタバミほど厄介なキャラではない😌
※塊茎(かいけい): 地下茎の一種で,養分を多量にたくわえて肥大したもの。

イモカタバミのイモ=塊茎
【イモカタバミ】とは
【学 名】Oxalis articulata Savigny
Oxalis=ギリシャ語の「oxys(酸っぱい)」
この属の植物にはしゅう酸を含み酸っぱいものが多いことからきている。
articulata は「節目のある」という意味。
【和 名】イモカタバミ(芋方喰)
【英 名】jointed woodsorrel 、Pink sorrel
【別 名】フシネハナカタバミ
もとは、フシネハナカタバミの亜種がイモカタバミ。後に呼び名が統一。
【科・属】カタバミ科 カタバミ属
【原産地】南アメリカ
ブラジル,ウルグアイ,パラグアイ,アルゼンチンなど広域の比較的標高の高い地域が原産である。国内では北海道から沖縄まで栽培されているが、台湾などでは腐敗しやすいとの報告もある。日本への渡来は、第二次世界大戦後に観賞用として導入されて以降、国内に広く帰化している。
Wikipedia
【開花期】4~9月
【特徴・草姿・草丈】
花弁は5枚。濃い紅紫色で、濃い紅色の筋が入る。花の真ん中も濃い紅色をしている。

イモカタバミの花は、中心部の色が濃い。
ちなみに下の写真はムラサキカタバミ

ムラサキカタバミ。よりおとなしい感じ。
植物体に蓚(シュウ)酸を多く含み、土壌が酸性化する事が知られている。
Wikipedia
小さく赤い花が案外可愛い🤗雑草扱いはちと可哀想😭
カタバミは【クローバー】ではない
ちなみに「クローバー」とはマメ亜科シャジクソウ属のことで
・シロツメクサ
・アカツメクサ
…などを指す。シロツメクサの三つ葉の見た目がカタバミの葉っぱの様子とよく似ているから混同されているが、
シロツメクサの花も葉も、カタバミとは全く異なっている。

お馴染みの【シロツメクサ】これが、クローバー。

シロツメクサの葉。白いV字の模様(斑紋)が入っている
ももいろクローバーZのロゴがカタバミの葉っぱの💛マークだったり、クルマに貼るクローバーマークも

クルマに貼る身体障害者標識【クローバーマーク】もカタバミの葉っぱ
外来の厄介な植物を間違えてデザインしてしまっている。
関連記事
シリーズ抜けない雑草【アカツメクサ】
植物fan.TaiChi