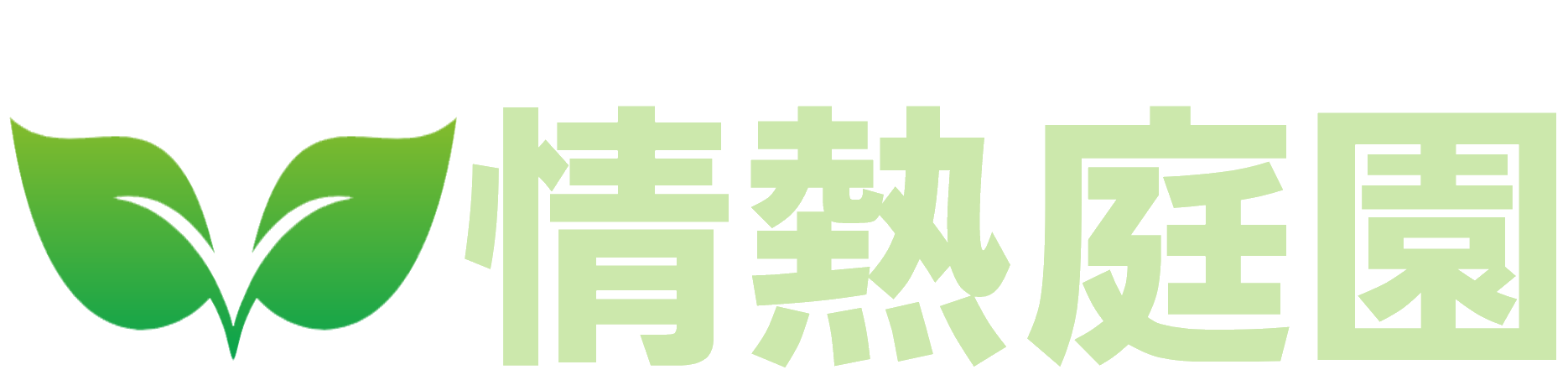Last Updated on 2024年9月21日 by Taichi
バラの2大病のひとつ…【黒星病】

バラの2大病のひとつ…【黒星病】
バラの病気として、『ウドンコ病』と並んで有名?なのが『黒星病』
『黒星病』は、バラ以外ではあまり聞かないですし、逆にバラは必ずといっていいほどかかる病気。
対応が遅れると…

【黒星病】9月、少し気温が下がると再び発生
秋雨前線と【黒星病】
気温20℃前後の過ごしやすい時期こそ要注意。
記事執筆中の9月初旬、熱帯?と思わせるスコールの連続ですが、
秋雨前線のこの時期…9~10月は【黒星病】が頻発する時期でもありますね。

黒星病って、どんな病気?
黒星病(別名 黒点病)
英名 : spotting; scab; black spot
黒星病とはバラの主要病害です。梅雨の時期や秋の長雨の時期を中心に気温20℃前後で長時間葉が濡れた状態になった時、湿度が高い時に多く発生します。

5月 黒星病に罹ったバラ 油断するとあっという間に落葉していく
カビ菌を原因とした病害で治すことが難しく、防除が大切になってきます。
とは言え、人にとっての風邪、くらいの病気だと思います。ほったらかしにしない限り、黒星病でバラ苗が枯れてしまうとは思いにくいので…
黒星病の発生 時期/場所
発生時期
黒星病(黒点病)が最も多く発生するのは5~6月、および9月中旬~10月中旬頃。
黒星病菌は10℃前後の比較的低温で活発化、25℃以上では発生が緩慢になりますが、雨が多いと感染が拡大するため、梅雨が長く、冷夏の年には夏でも発生します。
…要するにバラの成長期、バラのいい時期は黒星の発生時期ってこと。夏の酷暑が落ち着く時期など要注意。
発生場所
黒星病は若葉にはほぼ出ない。これが【うどん粉病】と違うところ。若い葉は保護皮膜にしっかりと守られており、黒星病への感染を防いでくれています。葉が成熟したころに感染しやすくなるのです。

バラの葉が成熟した頃に現れる【黒星病】
病原菌は越冬する
黒星病の病原菌は糸状菌というカビの仲間で、土の中にも水の中にも存在します。赤土よりも保水率の高い黒土の中に病原菌は多く存在します。そして雨で土のはね返りがあるとそこから侵入してきます。病原菌は、発病した葉や枝、落ち葉で越冬し、翌春に増えて新葉に伝染します。かなりマメにクスリを散布しても次のシーズンに繰り返し黒星病が発生するとしたら、それは病気になって落ちた葉っぱをそのままにしておくのが一番の原因では…
黒星病の対策
●マルチング
一般的な黒星病の防除法はマルチングが有効とされています。敷きワラを株元に施すのは、水の跳ね上がりを防止して、葉裏に菌が付着するのを防ぐためです。
●周辺をキレイに
黒星病は地中に潜んでいるので、落葉などは放置しないで速やかに焼却するか、ゴミ袋に回収しましょう。
●軒下管理
そもそも、雨に当てない。これは大きな予防策。
●クスリ
クスリで予防するなら、私が黒星病対策の使っているのは以下の2つ。【ベン・ダコ】です。
GFベンレート水和剤
ばらの黒星病、うどんこ病に優れた効果があります。浸透移行作用により病原菌の侵入を防ぐ予防効果と、侵入した病原菌を退治する治療効果を兼ね備え、病原菌の細胞分裂を阻害して防除します。特に黒星病には早春の萌芽前から散布することで防除効果が高まります。
※有効成分は【ベノミル】治療効果を兼ね備えているのはポイント。
STダコニール1000
●草花、野菜、果樹など様々な植物で、かび類(糸状菌)によって起こり、特にもち病や炭そ病、斑点病など葉が変色するタイプの広範囲の病気に効果がある優れた園芸用の総合殺菌剤です。
●耐光性、耐雨性に優れ、病気から植物を守る残効性があります。また各種病原菌に対しても抵抗性がつきにくい、優れた効果の保護殺菌剤です。
※有効成分は【TPN】
※最近のものでは『ベニカXガード粒剤』が評判◎です。
関連記事
バラはど~してもかかる《うどんこ病》
植物fan.TaiChi